
介護の仕事を辞めたい…でも本当に辞めていいのかな?
介護現場はやりがいがある一方で、人間関係や体力面、制度の限界など多くの壁があります。離職率は下がってきたものの、人手不足は依然として深刻。この記事では、介護職を辞めたいと感じる理由やその背景、性別・年齢・施設別の傾向、早期離職の要因、防止策、そして納得できる職場探しの方法までを採用担当者の視点も交えて詳しく解説します。読めば「辞めたい」気持ちを整理し、次の一歩が明確になるはずです。
「介護職を辞めたい…」そう思ったときにまず知っておきたいこと
💬「本当に辞めるべきか、それとも他の方法があるのか迷っています」
離職率は改善しても、人手不足が続く理由とは?
介護職の離職率は年々改善していますが、依然として人手不足は深刻です。
- 介護職の離職率は1年以内の離職が目立つ
- それでも約65%の事業所が「人手不足」と回答
- 特に訪問介護では8割が人材不足
これは単に「辞める人が多い」だけでなく、新たな人材が入ってこないことが大きな要因です。 さらに、高齢化による需要の急増も、供給体制の整備を追い越しています。
つまり、「辞めたい」と思うこと自体が特別ではなく、むしろ業界全体の構造的な課題でもあるのです。
「自分が弱いから」と責めずに、今の職場や働き方を見直すきっかけにしてもよいのではないでしょうか。
「辞めたい」の裏にある本音を知ることが大切
転職を考えるとき、大切なのは「感情」だけで動かないことです。
- 本当に辞めたい理由は何か?
- 職場を変えれば解決する問題なのか?
- 今の環境に不満があるだけなのか?
例えば、「人間関係がつらい」と感じるなら、
- 管理者のサポート体制
- チームの雰囲気
- 自分のコミュニケーションスタイル
を見直すだけで改善する場合もあります。
一方、「自分の将来像が見えない」「収入が上がらない」といった悩みであれば、 転職によって新たな選択肢が見えることもあります。
大切なのは、“何が嫌か”よりも、“何が叶えたいか”を明確にすること。
「辞めたい」から「自分らしく働きたい」へ、視点を変えてみませんか?
介護職の離職理由ランキングTOP5【2025年版】
💬「自分と同じ理由で辞めたい人って、どれくらいいるんだろう?」
介護職を辞めたいと感じる理由には、共通の傾向があります。
実際に多くの調査で明らかになっているのは、次の5つの理由です。
第1位:職場の人間関係がつらい
- 上司や先輩との関係が悪い
- 無視や陰口、パワハラなどのストレス
- チームワークの悪さで仕事が回らない
介護現場はチームで支え合う職場です。そのため、人間関係のストレスは業務全体に影響を及ぼしやすく、離職理由として最も多く挙げられています。
第2位:施設運営や方針への不満
- 管理者が現場の声を聞いてくれない
- 方針がコロコロ変わる
- 理念と実態にギャップがある
「いい介護がしたい」と思っても、組織の方針や運営体制とズレがあると、やりがいを感じられなくなってしまいます。
第3位:体力的な負担と業務内容
- 腰や膝を痛めるほどの身体的負担
- 夜勤やシフト勤務で生活が不安定
- 雑用ばかりでやりがいがない
特に入浴や移乗介助など、身体的な負担が続くと心身ともに消耗しやすくなります。
第4位:収入が見合わないと感じた
- 資格手当や昇給が少ない
- ボーナスが出ない/少ない
- 責任が重いのに給与が低い
収入面の不満も根強く、やりがいや使命感だけでは続けにくい現実があります。
第5位:やりたい介護ができない
- 利用者とゆっくり関われない
- 書類や雑務に追われている
- 自分の介護観と現場が合わない
「利用者さんの役に立ちたい」という気持ちと、実際の業務のギャップが大きいと、やりがいを見失ってしまいます。
この5つの理由は、単なる“わがまま”ではなく、現場で本当に多くの方が感じている悩みです。
あなたが感じているその迷いにも、ちゃんと理由があります。
まずは「同じように悩む人がいる」と知ることから、少しずつ次のステップを考えてみませんか?
あなたの悩みはどこから?性別・年齢・施設別で見る傾向
💬「今の職場だけが特別なのかな…?」
性別で異なる離職理由の傾向
- 男性
将来性や収入への不満が高い傾向があり、特に管理職や専門職へのキャリアパスが見えにくいことが原因として挙げられます。
また、家計の大黒柱としての責任から、より高収入を求めて異業種への転職を選ぶケースも多く見られます。 - 女性
結婚・出産・育児などライフイベントの影響が大きく、産休・育休制度の充実度や時短勤務の可否が継続勤務の鍵となります。
家庭と仕事の両立が難しい場合、離職を選ばざるを得ない状況になることも少なくありません。
年齢層による悩みの違い
- 若年層(〜29歳):将来性や収入、人間関係への不満が集中し、「このまま続けても成長できないのでは」という不安から転職に踏み切る傾向があります。
- 中高年層(30〜50代):介護の質や施設方針へのこだわりが強くなり、自分の介護観と合わない現場ではストレスが蓄積しやすくなります。また、管理職やベテラン職員としての責任負担も大きな要因です。
- 高年層(60歳〜):体力面の限界や、定年後の継続雇用条件の厳しさが課題です。待遇や勤務日数の希望が合わず、退職を選択するケースが増えています。
施設形態別に見る特徴
- 入所型:夜勤や重介助など身体的負担が大きく、特に腰痛や関節痛など健康面の理由で退職する人が多いです。加えて収入面への不満も根強くあります。
- 通所型:日勤中心で体力的負担は軽めですが、利用者数やサービス内容に関する意見が反映されにくいことへの不満が目立ちます。
- 訪問介護:比較的柔軟な働き方が可能で、近年は賃金改善も進み定着率は上がっていますが、移動時間や一人作業による孤独感が課題となることもあります。
H2. 早期離職が多いのはなぜ?1年以内の退職に共通する要因
💬「転職したばかりだけど、もう辞めたいと思ってしまう…」
入職前の理想と現実のギャップ
- 想像以上の身体的・精神的負担:腰痛や疲労、精神的ストレスなど、想定以上の負担が積み重なります。
- 利用者対応や介助業務の重さ:移乗や排泄介助など、日々の業務が体力を消耗させます。
- 現場の忙しさで理想の介護ができない:ゆっくり関わりたい気持ちがあっても、時間に追われて妥協せざるを得ない現実があります。
教育・サポート体制の不足
- OJTや研修が不十分:業務の流れや介助方法を十分に教えてもらえず、不安が増大します。
- 質問しづらい雰囲気の職場:聞きづらい空気や遠慮がミスや負担につながります。
- 業務理解が追いつかず挫折感:覚えることが多く、ミスを恐れて自信を失ってしまうケースも。
人間関係・職場環境への不適応
- 小規模職場で人間関係の逃げ場がない:メンバーが固定され、衝突が長期化しやすい環境です。
- 派閥や固定メンバーによる孤立:馴染めず孤立感が強まり、働き続ける意欲が低下します。
- 職場文化や価値観が合わない:介護観や仕事の進め方が合わず、モチベーションが保てません。
防止策
- 面接時に業務やシフトを具体的に確認:仕事内容・勤務時間・夜勤の有無などを詳細に把握します。
- 試用期間中にサポート体制や人間関係を観察:職員同士の会話や協力体制をよく見ることが重要です。
- 入職前に施設見学・体験勤務で雰囲気を把握:実際の現場で、自分に合うかどうかを見極めましょう。
制度改善は本当に効いている?処遇加算と働き方改革の現実
💬「給料や働き方って、良くなっているんですか?」
処遇改善加算の効果と限界
物価高騰の影響:給与が上がっても、生活費の上昇に追いつかないケースが多いのが現実です。
給与面での改善:処遇改善加算により、多くの介護職の基本給や手当に上乗せがされています。
限界も存在:加算は事業所の裁量で配分されるため、全員に均等ではなく、ボーナスや特定の職員に偏ることも。
残業削減や有休促進の取り組み
- 残業時間の見直し:シフト管理や業務分担の改善で残業を減らす動きが広がっています。
- 有休取得の促進:国の方針に沿って、有休消化率の向上を目指す施設が増加。
- 課題:利用者の急変や人員不足で、計画通りに休めない現場もまだ多い状況です。
ITツールの導入で変わる現場の働きやすさ
- 記録業務の効率化:タブレットや音声入力で、ケア記録や報告がスムーズに。
- 情報共有の迅速化:クラウド型システムで、スタッフ間の連絡が即時に可能。
- 導入の壁:機械操作に不慣れな職員や、初期費用負担の大きさがネックになる場合も。
【体験談】採用担当として見た「辞めずに続く人」の特徴
💬「長く続けられる人って、どんな共通点があるのかな?」
最初の面接で感じる「伸びる人」の共通点
- 質問力が高い:仕事内容や勤務条件を具体的に尋ね、自分の働き方と照らし合わせて考えられる。
- 現実的な期待を持っている:介護職の大変さを理解した上で応募しているため、ギャップで挫折しにくい。
- 表情や態度が前向き:面接中の笑顔や、素直な姿勢が好印象。
職場に馴染める人の特徴とは?
- コミュニケーションが柔らかい:自分の意見を持ちながらも、相手を尊重して話せる。
- 変化に柔軟に対応できる:利用者や業務の急な変更にも落ち着いて行動できる。
- 協力意識が強い:自分の仕事だけでなく、周囲のサポートにも積極的に関わる。
入社後すぐ辞めない人が持っている視点
- 長期的な視野:目先の不満やトラブルだけで判断せず、「数カ月後にはどうなっているか」を考えられる。
- 自己成長を楽しめる:失敗や注意も学びの機会と捉える姿勢。
- 環境改善の工夫:困難な状況でも、自分で働きやすくする方法を探す。
採用担当としての経験から言えるのは、「辞めずに続く人」は最初から特別なスキルを持っているわけではありません。現実を理解し、柔軟で前向きな姿勢を保てる人が、長く活躍できるのです。
無料でできることから始めよう|転職活動を始める前に
💬「辞める前に、他の職場も見てみたい…」
まずは求人を見比べてみるだけでもOK
- 視野を広げる第一歩:求人情報を眺めるだけでも、自分の市場価値や条件相場が見えてきます。
- 条件の優先順位を整理:給与・勤務時間・勤務地・福利厚生など、譲れない条件と妥協できる条件を明確にしましょう。
- 気軽に情報収集:応募や連絡をしなくてもOK。まずは比較して傾向を知ることが大切です。
気になる施設があれば、見学だけでも行ってみよう
- 現場の雰囲気を直に感じる:利用者や職員の表情、施設の清潔感などは求人票ではわかりません。
- 働く自分をイメージ:見学時にシフトや業務内容も具体的に質問してみましょう。
- 短時間でも効果大:数時間の見学でも、相性や働きやすさのヒントが得られます。
転職エージェントを使うと“独りで悩まない”転職ができる
- 非公開求人にアクセス可能:一般公開されていない好条件求人を紹介してもらえる場合があります。
- 条件交渉や面接調整を代行:給与・シフト・入社日の調整など、自分では言いづらいことも代理で対応。
- 悩みを共有できる相談相手:辞めたい理由や将来の希望を安心して話せるプロがいるのは心強いです。
転職活動は、必ずしも「辞表を出してから」始める必要はありません。まずは無料でできる情報収集や見学から始めれば、安心して次の一歩を踏み出せます。
【この記事のまとめ】あなたが“納得して働ける場所”を見つけるために
介護職を辞めたい理由は人によってさまざまですが、その背景には職場環境・人間関係・業務負担・制度の限界など、共通する課題があります。この記事で紹介した傾向や防止策を参考にすることで、同じ失敗を繰り返さず、自分に合う職場を見極めやすくなります。
今日からできる行動
- 求人情報をチェックし、条件や雰囲気を比較する
- 気になる施設を見学し、現場の空気を体感する
- 転職エージェントに相談し、非公開情報を得る
納得して働ける職場は、情報収集と冷静な判断から見つかります。焦らず、でも一歩ずつ行動して、あなたが笑顔で続けられる介護の仕事を見つけてください。
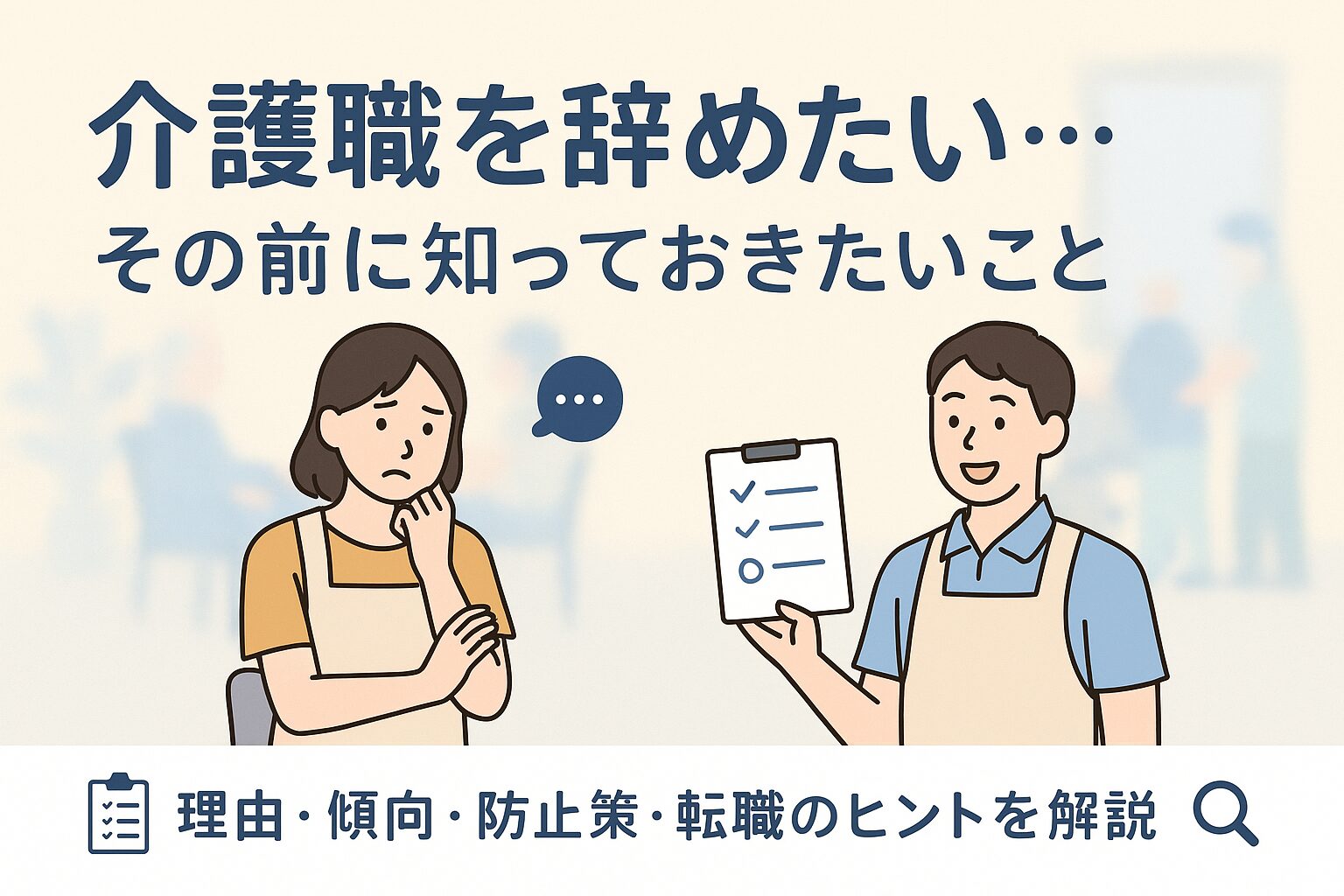

コメント